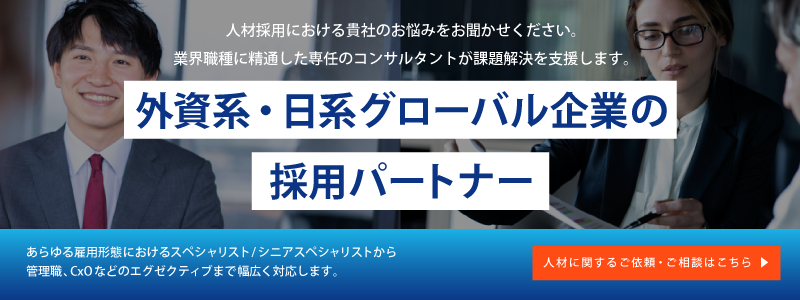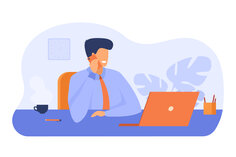公開日:

超高齢化社会に起きる「2025年問題」は、雇用にも多大な影響を及ぼすことが予想されています。この記事では、「2025年問題」で企業が受ける影響や備えるべきことなどについて、FAQ形式で解説します。
|Q. 2025年問題とは?
2025年以降にすべての団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)になると、65歳以上の高齢者の数が全人口の30%に膨れ上がることで「超高齢化社会」に突入します。
2025年問題とは、その際に雇用・医療・福祉などさまざまな分野で起こるといわれる社会的問題の相称です。
|Q. 2025年問題が企業に与える影響とは?
2025年問題は、一般企業にも次のような影響を及ぼすことが予測されるため、現時点から課題を把握し、解決策を練っておく必要があります。
会社の存廃を左右しかねない事業承継問題
中小企業庁によると、2025年までに中小企業・小規模事業者の経営者約245万人が70歳になります。引退年齢を迎えるにもかかわらず、そのうち約127万人の後継者が決まっていないのが現状です。後継者がいないため廃業する中小企業・小規模事業者が生み出すはずだったGDPは、22兆円にも及ぶとも試算されています。
人材確保の難しさ
高齢者が急増していく一方で、生産年齢人口(15歳以上65歳未満の生産活動の中心にいる人口)や出生率は減少を続けていくため、人材の確保は非常に難しくなります。
他にも2025年には4〜5人に1人が75歳となり、医療費の増大による税金の確保ができない、医師・看護師不足などの問題が生じると考えられます。 また、男性女性共に75歳という年齢は、平均寿命と健康寿命の節目を迎えるタイミングとなり、介護サービスの利用者もさらに増えることになります。
しかし、超高齢化社会では介護を必要とする高齢者と介護人材の需給バランスが大きく崩れるため、介護の財源も十分とはいえません。 そうなると自宅で介抱しなければならない人が増える可能性も考えられるため、より働き手が減少することが考えられます。
介護・育児との両立や副業・時短勤務など多様な働き方ができるのかやワークライフバランスが整っているのかなどが企業選びのポイントとなってくるため、柔軟な働き方に対応する制度や職場の雰囲気づくりが求められます。
|Q. 2025年問題に対する政府の取り組みとは
政府が2025年問題の解決のために推進している取り組みを3つ説明します。
介護離職者ゼロへの取り組み
厚生労働省では家族の介護を理由とした離職を防止するため「介護離職ゼロ」の取り組みを推進しており、介護人材の育成のための制度や処遇改善を行っています。また、介護士を目指す外国人留学生の受け入れや介護ロボットの導入を促進するような施策も行っています。
高齢者の再雇用推進
高齢者の再雇用を推進するためには、シルバー人材センターなどとの連携を行い就業意欲のある中高年齢者の発掘及び企業とのマッチングを行ったり、希望すれば60歳以降も賃金を過度に引き下げることなく継続して企業に勤められるような給付金の支給を行ったりしています。
地域包括ケアシステム
政府は、高齢者が人生最後のときまで住み慣れた土地で自分らしい暮らしが続けられるよう、住まい・医療・予防・介護・生活支援を切れ目なく一体的に提供できるような「地域包括ケアシステム」の拡充にも努めています。
|Q. 2025年問題に企業が備える対策とは?
企業が取り組むべき対策の主な例を紹介します。
公的機関の支援による事業継承
企業は、公的機関の支援を活用しながら事業継承を進める必要があります。 中小企業庁は経営承継円滑化法による次のような支援を実施しています。
- 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予および免除制度)の前提となる認定
- 金融支援(中小企業信用保険法の特例・日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
- 遺留分に関する民法の特例
ダイバーシティ推進による人材の多様化
人手不足の解消には、人材の多様化も必要です。女性労働者や高齢者、外国人労働者の力を生かせる多様な働き方を認め、その多様性を生かすダイバーシティの推進が、あらゆる企業に求められています。
離職防止
離職防止のためには、ワークライフバランス支援をはじめとした施策が重要です。 フレックスタイム制やテレワーク制度などを導入し、仕事と家庭が両立できる社内制度を整備しましょう。
今回は2025年問題について解説しました。エンワールドは、企業のグローバル人材に関する採用課題をあらゆる方面からサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。