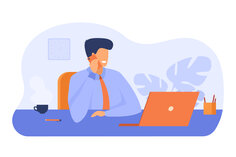公開日:
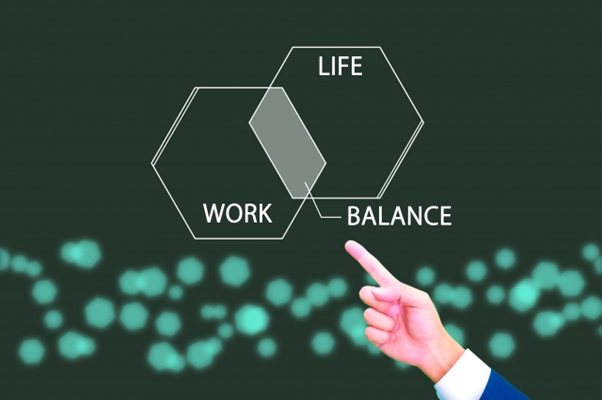
近年、「働き方改革」という言葉とともに労働への考え方が多様化していく中で、「ワークライフバランス」という言葉を耳にする機会も多くなったのではないでしょうか。
この記事では、ワークライフバランスの意味や重視される理由、推進によるメリット・デメリットや取り組みの具体例についてFAQ形式で解説します。
ワークライフバランスとは?
「ワークライフバランス」は、日本語で「仕事と生活の調和」と訳されます。
また、内閣府のサイトでは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること」と定義されています。
「ワークライフバランス」というと、仕事と生活の優先度や比重を決めるものだと感じる方もいるようですが、本来は仕事と生活を両立させて相乗効果を生むことを意味します。
なぜワークライフバランスを重視するのか?
高度経済成長の終焉や少子高齢化、男女雇用機会均等法などにより、現代の労働に対する考え方は多様化しています。「労働生産性」や「働き方改革」が重要視される中、その有効な打ち手のひとつとしてワークライフバランスを積極的に推進する企業が増えてきました。
なぜなら、ワークライフバランスの実現によって、従業員がプライベートで得たものを仕事に活かせたり、オンとオフの切り替えによって業務効率化が期待できると考えられているからです。
また、企業のこうした取り組みが定着・浸透すれば、従業員のモチベーションアップや従業員の職場定着率向上が期待でき、優秀な人材獲得における有利な交渉材料ともなり得ます。
ワークライフバランス推進のメリット・デメリットは?
ここでは、ワークライフバランスを推進する上でのメリットとデメリットを紹介します。
メリット
ワークライフバランスは、従業員と事業者の双方にメリットがあります。
まず、事業者側の主なメリットは以下の通りです。
- プライベートの充足によって従業員満足度が向上し、モチベーションの向上が期待できる
- 上記よって従業員の心身の健康を保護でき、業務効率化も期待できる
- 企業イメージの向上による優秀な人材の獲得、その後の定着率向上に繋がる
- 長時間労働の改善、生産性の向上による人件費の抑制が期待できる
次に、従業員側の主なメリットは以下の通りです。
- 個人が抱えるプライベートな事情(子育てや介護など)と仕事が両立しやすくなる
- 自分のための時間を創出でき、リフレッシュやスキルアップの時間が確保しやすくなる
- 上記によって仕事に打ち込むことができ、モチベーションの維持・向上に繋がる
デメリット
ワークライフバランスの推進するデメリットは、主に事業者側にあります。
- ワークライフバランスの見直しにより、従業員の労働時間が減少することで人手不足に陥り、短期的には生産性が下がる可能性がある。
- 急にワークライフバランスのために制度や仕組みを変えようとしても、現在の人事制度や評価制度との整合性がとりづらい。
- ワークライフバランスの推進には工数やコストがかかり、経営者や上層部の理解と協力が得にくい。
ワークライフバランスの取り組みの具体例は?
最後に、ワークライフバランスの実現に向けた取り組みの事例を紹介します。
所定外労働時間の削減を目的とした施策の実施
所定外労働時間を削減するために、ノー残業デーやノー残業ウィークなどを設定することで、従業員の定時帰宅を推奨する方法があります。また、業務の繁閑に合わせて部門休日を設定することで、年間の労働時間を平準化させるといった事例もあります。
体制整備や連続休暇の推奨による年次有給休暇取得の促進
年次有給休暇の取得を促進するために、組織内で定期的に個人の業務進捗を確認し、お互いに業務をカバーし合えるような体制を整備した事例もあります。
また、週末に合わせた休暇の取得を推奨し、「3連休」という形で有給休暇取得を促進している企業もあります。
その他、次のような事例もあります。
- 育児や介護に携わる従業員などが短い勤務時間で働ける「短時間勤務制度」
- 1ヶ月などの期間で総労働時間を規定しその枠内で始業・就業時間を自由に決められる「フレックスタイム制度」
- オフィス以外の場所で業務ができる「テレワーク制度」
- レジャー・宿泊施設・ジムなどの利用や資格取得支援などの「福利厚生サービスの充実」
- 女性による育児休暇だけでなく、男性育児休暇(パタニティリーブ)取得の促進
今回はワークライフバランスについて解説しました。エンワールドは、企業のグローバル人材に関する採用課題をあらゆる方面からサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。