公開日:
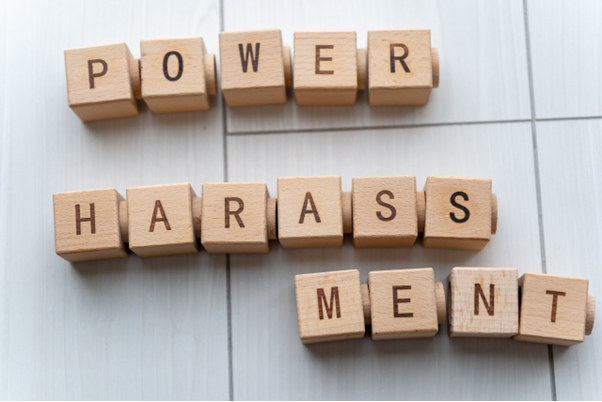
2019年5月に「パワハラ防止法」が成立し、企業には職場におけるパワハラを防止する措置が義務づけられるようになりました。
この記事では、「パワハラ防止法」についてまだよく知らない方のために、パワハラ防止法の要素や定義、パワハラ防止対策とそれを怠った場合のリスクについてFAQ形式で解説します。
パワハラ防止法とは?
正式名称は「労働施策総合推進法」といい、職場におけるいじめや嫌がらせを防止する対策として、企業にハラスメント防止の措置を義務付けたものです。2019年5月に成立し、2020年6月(中小企業は2022年4月)から施行されています。
この法律では、事業主が雇用管理上で講じるべき措置として、以下の4つの項目が明示されています。
- 社内方針の明確化と周知・啓発
- 適切に対処する体制整備
- 相談者の不利益な取り扱い禁止
- パワハラ事案への迅速かつ適切な対応
パワハラの3つの要素と6つの定義とは?
まずは、パワハラの概念について「3つの要素」と「6つの定義」に分けて解説します。
3つの要素
厚生労働省は「職場のパワーハラスメント防止のための指針」で、パワハラの概念を次の3つの要素を用いて説明しています。
- 優越的な関係にもとづいて(優位性を背景に)行われること
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
優越的な関係とは、職位や職能が高い人と立場的に逆らえない人との間柄を指します。この関係性において、仕事の範囲を超えた干渉はパワハラであるとしています。
6つの定義
厚生労働省は、上記3つの要素を満たすものを更に6つの類型に分けてパワハラを定義しています。
- 身体的な攻撃(殴る・蹴る・物を投げるなどの暴力)
- 精神的な攻撃(侮辱・人格否定・執拗な叱責など)
- 人間関係の切り離し(無視する、イベントに参加させないなどの仲間外れ)
- 過大な要求(明らかに無理な仕事の要求、私的な雑用の強要など)
- 過小な要求(仕事を与えない、お茶汲みの義務化など)
- 個の侵害(業務外に対する過度な詮索・関与、家族や恋人の悪口を言うなど)
どこからどこまでがパワハラなのか?
どこからどこまでがパワハラの範疇なのかを判断するには、先ほど紹介したパワハラの範疇を示す客観的な基準(3つの要素・6つの定義)が参考になります。
ただし、パワハラかどうかの判断は主観によるところが大きく、どこからどこまでがパワハラなのかを断定することは難しい場合もあります。
6つの定義について、下記のケースはパワハラには該当しないので、併せてパワハラに該当するかの判断の参考にしてください。
6つの定義に該当しないケース
1)身体的な攻撃:誤ってぶつかる
2)精神的な攻撃:社会性を欠いた言動を繰り返す労働者に強く注意する
3)人間関係の切り離し:育成・短期間集中を目的に別室で研修を実施する
4)過大な要求:育成を目的に少し高いレベルの業務を任せる
5)過小な要求:労働者の能力に応じて業務を軽減する
6)個の侵害:配慮を目的として病状などの個人情報をヒアリングする
パワハラ防止対策を怠るリスクとは?
パワハラの防止対策を怠った場合、企業にはさまざまなリスクがもたらされる可能性があります。
例えば、男女雇用機会均等法などの法令違反に問われる「コンプライアンス・リスク」や、それらがメディアに取り上げられたり訴訟になったりすることで社会的信用を失う「レピュテーション・リスク」が挙げられます。
これらは、従業員のエンゲージメントや企業イメージにもネガティブな影響を与えることになるでしょう。
また、パワハラの被害にあった従業員がメンタルヘルス障害を起こしてしまう「メンタルヘルス・リスク」も考えられ、彼らに対する賠償責任が生じる可能性もあります。
ハラスメントを防止するために、人事および企業がとるべき対策とは?
企業には、パワハラ防止法をはじめとする法律によって以下の対応が義務付けられています。その多くは人事労務に関するものなので、人事が主導となって対策を講じていきましょう。
パワハラ防止対策の方針を決定し、社内で周知・啓発する
まずは、パワハラに該当する内容を周知させるとともに、管理監督者を含む全ての従業員に発生防止を啓発していきます。社内研修の実施に加え、就業規則や社内報なども活用するとよいでしょう。
また、実際にパワハラが発生した際には厳正に対処し、その内容を全従業員へ周知することで再発防止を啓発しましょう。
パワハラに関する相談窓口の設置
パワハラの相談窓口を設置することで、早期に発見できるような仕組みを作っておくことも大切です。予め相談窓口の担当者と連絡先を決めておくほか、従業員に定期的にアンケートを実施する、または外部機関に窓口業務を委託することで従業員が社内のことを気軽に相談できるようにするなどといった方法があります。
今回はパワハラ防止法について解説しました。エンワールドは、企業のグローバル人材に関する採用課題をあらゆる方面からサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。



